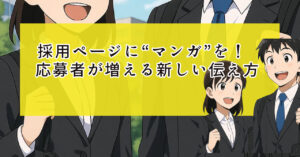マンガの力がここに極まる!心と社会を動かすプラットフォーム
「たかがマンガ」と侮るなかれ——。
今、マンガは単なる娯楽を超え、社会を動かすほどのインパクトを持つメディアへと進化しています。物語が人を動かし、キャラクターが地域を活性化し、デジタル技術によって世界へと広がっていく。そんな時代に、私たちはどのようにマンガと向き合い、活用していくべきなのでしょうか。
この記事では、マンガが持つ秘められた力を、「地域」「世界市場」「IP戦略」「ファン体験」そして「Webサイトでの活用」という5つの視点から紐解いていきます。2025年、マンガの可能性はここまで来ている——その現実と未来を、ぜひ一緒に探ってみましょう。
- 1. マンガが地域を動かす——「聖地巡礼」と地方創生の力
- 1.1. 熊本県「ONE PIECE」の事例
- 1.2. 大分県日田市「進撃の巨人」の事例
- 2. マンガが世界を魅了する——急成長するグローバル市場
- 2.1. 世界と日本の市場規模の推移
- 2.2. デジタルとウェブトゥーンの台頭
- 3. IPコンテンツとしての爆発力——メディアミックスと経済効果
- 3.1. アニメ・映画・ゲームなどへの展開
- 3.2. アニメ起点の海外展開事例
- 4. 体験価値とファンエンゲージメント——没入と共感を生む仕組み
- 4.1. アート展・コラボカフェによる没入体験
- 4.2. ファン層の拡大とロイヤルカスタマー化
- 5. なぜWebサイトに「マンガ」が効くのか?
- 5.1. 直感的に伝わるストーリーテリング
- 5.2. 離脱防止と滞在時間の向上
- 5.3. ブランドイメージの明確化と感情の共鳴
- 6. マンガがもたらす未来——ビジネスと文化をつなぐ架け橋
- 7. まとめ
- 7.1. 資料
ページ内容
マンガが地域を動かす——「聖地巡礼」と地方創生の力
マンガの舞台となった地域を実際に訪れる「聖地巡礼」。かつてはファンの間で密かなブームに過ぎなかったこの行動が、今や地方自治体や観光業界にとって無視できない経済的・文化的現象となっています。マンガ作品が地域と連携し、観光需要を喚起することで生まれる効果は想像以上に大きく、データとしてもその影響力が明らかになっています。
熊本県「ONE PIECE」の事例
熊本県は2016年の地震復興をきっかけに、県出身の漫画家・尾田栄一郎氏が手がける「ONE PIECE」とタッグを組み、作中のキャラクター像を県内各地に設置しました。特に、主人公ルフィの銅像は2019年に約5万5千人の訪問者を呼び込み、26億7千万円以上の経済効果をもたらしたとされています。さらに、訪日外国人旅行者の滞在率も前年比2倍以上、宇土市では最大7.33倍に増加しました。マンガの力が、復興支援と観光振興の両面で地域に深く貢献していることがわかります。
大分県日田市「進撃の巨人」の事例
同様に、大分県日田市では「進撃の巨人」の作者・諌山創氏の出身地という縁から、キャラクター像の設置や専用ミュージアム「進撃の巨人 in HITA」を開設。年間訪問者数は約7万人を超え、年間20億円の直接経済効果、経済波及効果は30億円以上と推計されています。自治体のプロモーションだけでなく、地元市民と作品ファンの協力による温かい地域づくりが、継続的な観光と経済循環を生み出している好例です。
これらの取り組みは、マンガが単なるエンターテインメントを超え、地域を動かし、人を惹きつける“コンテンツパワー”であることを証明しています。
マンガが世界を魅了する——急成長するグローバル市場
マンガは今や、日本国内だけで消費されるコンテンツではありません。海外でも広く受け入れられ、多くの国と地域で「JAPANESE MANGA」という言葉が通じるほど、その存在感を増しています。その成長は数字にもはっきりと表れています。
世界と日本の市場規模の推移
2010年から2021年の11年間で、世界のマンガ・コミック市場は約8,400億円から1兆1,800億円へと拡大し、年平均3.4%という安定した成長率を維持しています。日本国内においても、出版市場全体が縮小傾向にある中で、マンガ市場はむしろ逆行するように拡大し、2021年には7,000億円を突破。出版市場全体に占めるマンガの割合は、2010年前後の20%から2021年には約40%に迫るほどになっています。
この成長は一過性のブームではなく、持続的な消費者の支持によるもの。世代を超えて読み継がれる作品、次々に登場する新たなヒット作、そして多様なジャンルの広がりが、読者層を拡大しています。
デジタルとウェブトゥーンの台頭
近年の成長をさらに加速させているのが、電子コミックとウェブトゥーンの存在です。韓国発の縦読みマンガ「ウェブトゥーン」は、スマートフォンでの閲覧に最適化された新しいマンガフォーマットとして急速に広がり、グローバル市場を牽引しています。
たとえば、NaverWebtoonのグローバルユーザー数は8,560万人に達し、過去5年で年平均14%の成長を遂げています。また、ウェブトゥーン市場は2021年に0.5兆円だった規模が、2028年には3.7兆円に達すると予測されており、実に6倍以上の成長が見込まれています。
日本国内でも、漫画アプリの利用が急増しており、上位6アプリの月間利用者数(MAU)は2019年からの2年間で2.3倍以上に増加。このようなデジタル環境の進化は、若年層を中心とした新たな読者層の獲得と、グローバルな読者接点の創出を可能にしています。
マンガは、言語や文化の壁を越え、世界中の人々に共感と興奮を届けるコンテンツとして、その市場価値を高め続けています。次なる成長の鍵は、さらに多くの国・地域との接点をどう作るか。その挑戦は、すでに始まっているのです。
IPコンテンツとしての爆発力——メディアミックスと経済効果
マンガの魅力は、紙面上の物語だけに留まりません。その強い物語性とキャラクター性は、他のあらゆるメディアとの融合を可能にし、「IP(知的財産)」として多様な展開を遂げています。この“メディアミックス”の力こそ、マンガが持つ圧倒的な経済効果の源泉です。
アニメ・映画・ゲームなどへの展開
マンガを原作とするアニメ、映画、ゲーム、さらにはキャラクターグッズやテーマパークまで——一つの作品が展開できるフィールドは実に広大です。ある人気漫画のIP展開では、累計860億ドル(約13兆円)の売上を記録した事例もあり、そのスケールは国を越えた経済圏を形成していると言っても過言ではありません。
たとえば「名探偵コナン」や「ドラえもん」は、それぞれ20作品以上で1作品あたり10億ドル超の収益を上げており、継続的な劇場版公開によってシリーズ全体の価値を高めています。また、「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」は、わずか2作品で1億6,600万ドルの興行収入を記録し、全世界で大ヒットとなりました。
このような成果は、マンガが起点となり、他の表現メディアにシームレスに変換されていく柔軟性の高さを物語っています。
アニメ起点の海外展開事例
海外市場において、マンガを知る最初のきっかけはアニメであることが非常に多いのが現実です。たとえば「鬼滅の刃」は、英語圏では劇場版アニメ公開時にGoogle検索数が急増し、その後に原作漫画への関心が高まりました。これは「アニメ→原作」の流れを生み出す典型的なパターンです。
こうした展開を通じて、海外のアニメファンを原作の読者へと誘導し、IP全体の価値と収益を最大化していく戦略が今、世界中で展開されています。出版社も自社アプリやグローバルプラットフォームを活用し、作品を多言語・同時配信することで、リアルタイムでのファン獲得を実現しています。
マンガIPは、ただの物語にとどまらず、「ビジネスの核」となりうる巨大な価値を秘めています。その爆発力を活かすかどうかは、私たちの“展開力”次第なのです。
体験価値とファンエンゲージメント——没入と共感を生む仕組み
現代のマンガファンは、「読む」だけでは満足しません。作品の世界観を“体験”し、登場キャラクターと“感情を共有”することに、より強い満足を求めています。こうした体験型コンテンツは、ファンの熱量を高め、ブランドへの愛着を深める手段として非常に効果的です。
アート展・コラボカフェによる没入体験
人気作品の原画を高品質な印刷で再現したアート展「集英社マンガアートヘリテージ トーキョーギャラリー」では、展示とNFT技術を組み合わせることで、マンガ作品の“アートとしての価値”を高める試みがなされています。ファンにとっては、作品への新しい触れ方であり、コレクションの一部としての満足感も大きな魅力です。
また、「JUMP 50th anniversary cafe」のようなコラボカフェでは、マンガの世界観を料理や空間で再現。キャラクターをイメージしたドリンクやメニューに囲まれて過ごすことで、ファンは一歩作品の“中”に踏み込んだような没入体験を得ることができます。
ファン層の拡大とロイヤルカスタマー化
これらの体験は、既存のファン層をより深く作品に引き込むだけでなく、これまでマンガに興味がなかった人々、たとえばアートファンや外国人観光客、家族連れといった新規層を作品の世界へと引き込む“入り口”にもなっています。
ファンが「体験」を通じて感情的なつながりを持つと、SNSでのシェアや口コミが活発になり、新たなファンを巻き込む好循環が生まれます。これは単なるプロモーションではなく、“エンゲージメント戦略”として非常に効果的です。
実際、アート展やイベントを通じて作品に出会ったユーザーが、原作を読み始めたり、関連グッズを購入することで**LTV(顧客生涯価値)**が大きく向上した事例も少なくありません。
マンガは、文字と絵だけでなく、五感と感情を刺激する「体験コンテンツ」として進化を続けています。この没入体験の設計こそが、ファンとの持続的な関係を築く鍵となるのです。
なぜWebサイトに「マンガ」が効くのか?
マンガのもつ力が、地域や世界経済だけでなく、Webマーケティングの現場でも大きな成果を生んでいることをご存じでしょうか。特に自社サイトやLP(ランディングページ)などにおいて、マンガは「伝える」「惹きつける」「記憶に残る」の3拍子を兼ね備えた、非常に優れたコンテンツなのです。
直感的に伝わるストーリーテリング
マンガは、ビジュアルとストーリーが一体となって情報を伝えるメディアです。難解なサービス説明や複雑な仕組みも、キャラクターと物語を通じて「一目で理解できる」ようになります。
これは特に、商品・サービスの導入ハードルが高い分野(金融・不動産・医療など)で大きな効果を発揮します。
たとえば、実際に企業紹介マンガを使った企業では、「文字だと離脱されていた説明部分」が、マンガにすることで完読率が3倍以上に向上したという事例もあります。
離脱防止と滞在時間の向上
Webサイトにおいて、ユーザーの「離脱」は致命的です。いかにページの滞在時間を延ばすかがコンバージョン率を左右します。
マンガには「先が気になる」構成と「視覚的に引き込む」魅力があるため、スクロール率や滞在時間の大幅な向上が見込めます。
Googleアナリティクスでの分析でも、マンガコンテンツを含むページは、そうでないページに比べて平均滞在時間が1.5~2倍に伸びたというレポートも存在します。
ブランドイメージの明確化と感情の共鳴
マンガは単なる説明ツールではなく、“企業の世界観”を可視化するブランディングツールとしても優れています。
企業の理念やサービスの価値を、キャラクターや物語の力で“感情に訴えかける”ことで、閲覧者に強い印象を残し、信頼や好感を獲得することができます。
特に、近年では「感情に訴えるマーケティング」が成果を上げている中で、マンガのストーリーテリングはまさにその最前線。読者に「自分のことのようだ」と感じさせることができれば、それは確実に“行動”につながるのです。
マンガは「視覚」「感情」「理解」の3つを一度に刺激できる、唯一無二のWebコンテンツです。ビジネスの成果を求めるWebサイトにこそ、導入する価値があるのです。
マンガがもたらす未来——ビジネスと文化をつなぐ架け橋
マンガは今や、日本の文化を象徴する存在として、世界中から注目を集めています。しかしその魅力は、エンターテインメントに留まらず、**ビジネスと文化の間をつなぐ「架け橋」**としても力を発揮し始めています。
企業や自治体がマンガを活用する事例は、観光振興や商品PRにとどまらず、ブランディング、CSR、採用活動、さらには海外展開のツールとしても広がりを見せています。ストーリーとキャラクターの力を通じて、人々の「共感」を生み、心を動かす力は、あらゆる領域で価値を発揮しています。
たとえば、海外配信を前提にした多言語展開や、電子コミックによる低コスト流通は、日本発のマンガをより多くの人々に届ける新たな道を開いています。出版社自身がプラットフォームを運営し、世界中の読者とリアルタイムに繋がる取り組みも始まっており、今後は“国境を超えたファンダム形成”がビジネスの新しい礎となっていくでしょう。
また、マンガは若年層だけでなく、あらゆる世代にアプローチできる柔軟性も兼ね備えています。教育現場や医療現場など、より公共性の高い分野での活用も進み始めており、「伝える」から「変える」ツールへとその立ち位置が変化してきています。
マンガは、人々の心を動かし、共感を生み出し、文化を越えてつながる力を持つ「21世紀の共通言語」です。
これからの社会やビジネスにおいて、マンガはますます重要な役割を担っていくでしょう。そしてその中心には、ストーリーを届けようとする“あなた”の視点と行動があるのです。
まとめ
マンガは単なる娯楽ではなく、地域を活性化し、世界市場で拡大を続け、メディアミックスで経済効果を生み出す“コンテンツの王様”です。そのストーリーテリングの力、ビジュアルの訴求力、そして体験を通じた共感の創出は、ビジネスのあらゆる分野に応用が可能です。
Webサイトにおいても、直感的な理解促進、滞在時間の延長、ブランディング効果の向上といった、具体的なメリットをもたらします。今や、企業活動にマンガを“どう活かすか”は、ブランド価値や顧客との関係構築を左右する重要な選択肢となっています。
2025年、マンガは文化とビジネスの架け橋として、さらに大きな可能性を秘めています。
そこであなたのWebサイトやプロジェクトに、「マンガブレンド」の力を取り入れてみませんか?
「伝えたいことがうまく伝わらない」「もっと心に響くコンテンツが欲しい」——そんなお悩みをお持ちの方にこそおすすめしたいのが、LPマンガの導入や診断コンテンツとの組み合わせ、そして**マンガ形式の入力フォーム(マンガフォーム)**です。
ストーリー性とビジュアル訴求を融合させたマンガブレンドなら、
✔ サービスの魅力を直感的に伝えるLPマンガ
✔ ユーザー体験を向上させる診断×マンガコンテンツ
✔ コンバージョン率を高めるマンガフォーム
といった形で、ユーザーとの接点を劇的に変えることが可能です。
もし「自社でも活用できるのか?」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。あなたの課題に最適な“ストーリー設計”をご提案いたします。
現在無料でマンガのプロットをプレゼントしています!
資料
資料:業界の現状及びアクションプラン(案)についてhttps://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/entertainment_creative/pdf/003_04_03.pdf
投稿者プロフィール

- 【北海道札幌市西区】でマンガLP制作や、マンガ活用フォーム、ウェブ担当・ウェブマーケティング・HP制作・SEO/MEOサービスをしている山本です。→🎁無料相談でマンガプロットプレゼント
最新の投稿
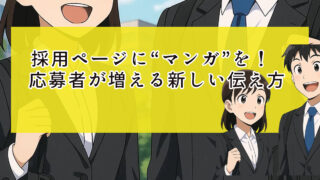 マンガコンテンツ2025年8月4日採用ページに“マンガ”を!応募者が増える新しい伝え方
マンガコンテンツ2025年8月4日採用ページに“マンガ”を!応募者が増える新しい伝え方 マンガコンテンツ2025年6月26日マンガの力がここに極まる!心と社会を動かすプラットフォーム
マンガコンテンツ2025年6月26日マンガの力がここに極まる!心と社会を動かすプラットフォーム AI2025年3月24日AIツールが苦手なもの6つまとめ
AI2025年3月24日AIツールが苦手なもの6つまとめ AI2024年6月21日中小企業・個人事業主必見!AIとDXで業務効率化を実現
AI2024年6月21日中小企業・個人事業主必見!AIとDXで業務効率化を実現